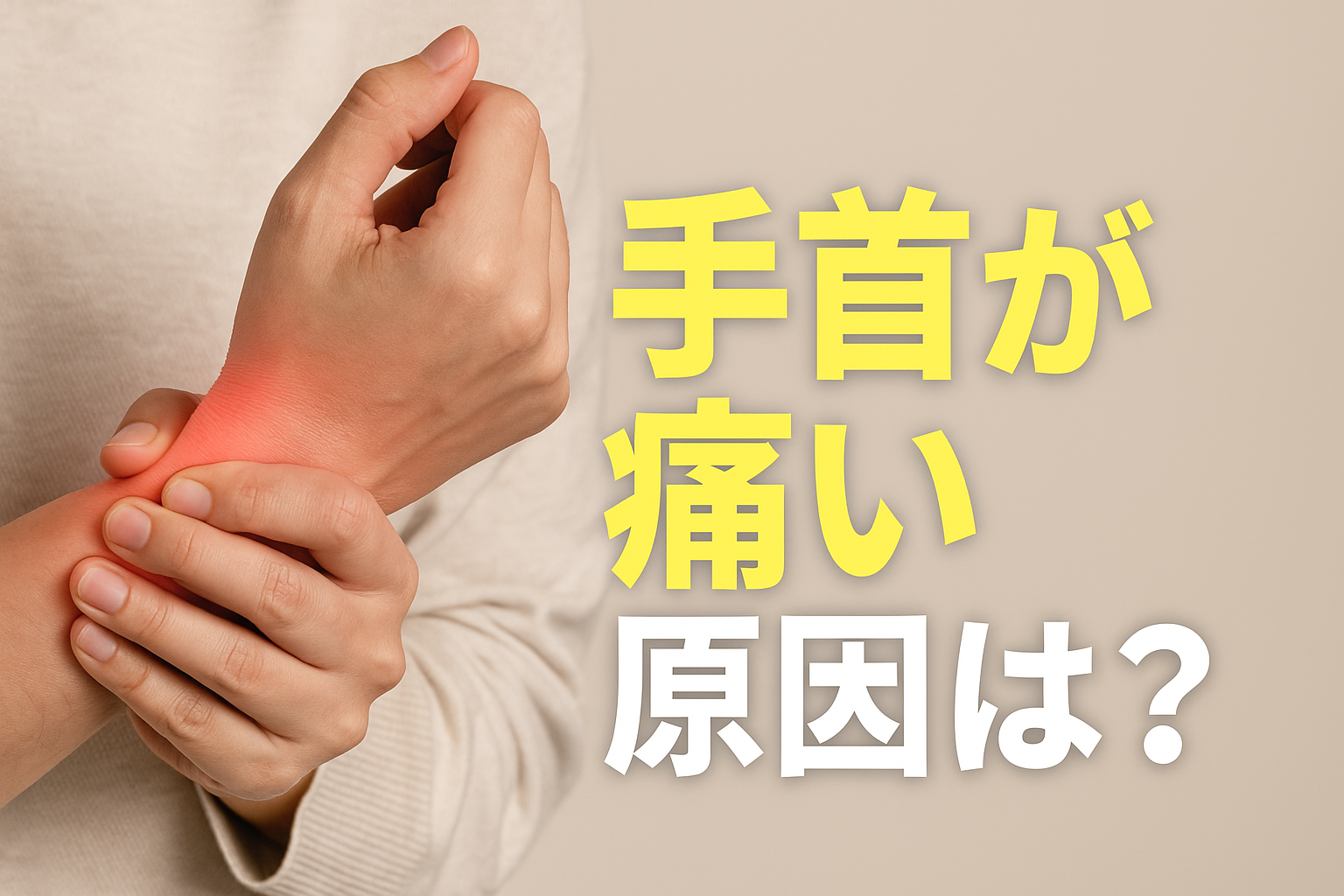手首が痛い…その「困った状況」とは?
手首の痛みの傾向とは?
「手首が痛い」と感じる場面って、意外と身近にありますよね。
たとえば、「ズキッと鋭い痛みが走る」「じんわり鈍い痛みが続いて気になる」など、感じ方に差があります。ある人は「手を動かした瞬間にピリッと痛む」と言い、また別の人は「朝起きたら手首が固まって動かしづらい」といった違和感を訴えるケースもあるようです。
なかには、「小指側だけが痛くて、スマホを持つのもつらい」とか、「親指のつけ根あたりがズーンと重たい」と感じる人も少なくありません。こうした痛みの出方は、腱鞘炎や関節の炎症、TFCC損傷などにつながる可能性があるとも言われています。
特に多いのが、スマートフォンの長時間使用による手首の負担です。片手でスマホを持ちながら親指だけを動かすという動作は、手首に大きなストレスをかけていると考えられています。
また、パソコン作業中にマウスを長時間操作する人や、タイピングが多い人も要注意。手首の角度が固定された状態が続くと、関節や腱に負担がかかりやすくなるとされます。
日々の小さなクセや何気ない行動が、手首に思った以上のダメージを与えているのかもしれません。まずは日常の中で、どんなときに手首が痛くなるのか意識してみることが大切だとされています。
(引用元:https://www.mediaid-online.jp/clinic_notes/information/778/)
#手首が痛い
#スマホ腱鞘炎
#パソコン作業と手首負担
#朝の手首の痛み
#転倒による手首の違和感
手首痛の主な原因と見分け方
腱鞘炎(ドケルバン病)〜親指側がズキンと痛む?
「最近、親指の付け根がズキッとする」「スマホを持っているだけでツラい」と感じている方、それは“ドケルバン病”と呼ばれる腱鞘炎の可能性があるかもしれません。
この症状は、親指を動かすときに手首の親指側に鋭い痛みが走るのが特徴と言われています。特に、赤ちゃんの抱っこやスマホの長時間使用で発症することが多いとされます。
自宅でできるチェック方法として、「フィンケルシュタインテスト」があります。親指を握った状態で手首を小指側に曲げると痛みが強くなる場合、腱鞘炎の可能性があるとも言われています。
(引用元:https://www.anchor-clinic.jp/)
TFCC損傷〜小指側の奥の痛み、感じたことありませんか?
「ペットボトルをひねった瞬間、手首が痛む…」という経験はありませんか?こういったケースでは、“TFCC損傷”が疑われることがあるそうです。
これは手首の小指側にある軟骨が損傷して起こる症状で、手首をひねるような動作や負荷のかかる動きで悪化する傾向があるとされています。
外見には腫れなどの変化が見られにくいこともあり、見落とされがちですが、違和感が長引く場合は注意が必要と言われています。
捻挫・骨折〜見た目にも分かりやすい変化が出やすい?
転倒やぶつけたあと、手首が腫れていたり、変形していたりする場合、捻挫や骨折の可能性があるそうです。ズキズキするような痛みが強く、動かすのも難しい状態であれば、放置せずに検査を検討することがすすめられています。
外傷後すぐは腫れだけで済んでいるように見えても、時間が経つにつれて内出血や骨のズレが明らかになることもあるため、経過を見て判断することが大切だとされています。
手根管症候群・関節炎〜朝の手首のこわばり、感じていませんか?
「朝、手首が動かしづらい」「指がしびれる」などの症状が続くときは、手根管症候群や関節炎の影響が考えられるとも言われています。
特にデスクワークが多い方や、更年期に差しかかる女性に多く見られる傾向があるようです。夜間や早朝に症状が強くなるのが特徴ともされており、生活スタイルとの関係性も注目されています。
#手首痛の原因
#腱鞘炎の見分け方
#TFCC損傷とは
#捻挫や骨折の兆候
#朝の手首のしびれ
今すぐできる!セルフチェック&対処法
手首痛のセルフチェック方法
「これって放っておいても大丈夫かな…?」そんなとき、まず試したいのが“セルフチェック”です。誰でも簡単にできる方法があるので、自宅で確認してみましょう。
まずは【フィンケルシュタインテスト】。これは腱鞘炎(ドケルバン病)が疑われる場合に使われるテストです。親指を内側にして拳を握り、そのまま手首を小指側に曲げてみてください。このとき鋭い痛みを感じたら、腱鞘炎の可能性があるとも言われています。
次に、【TFCC誘発テスト】も参考になります。小指側の手首を押しながら、ドアノブをひねるような動作をしてみてください。その動作で痛みが増す場合は、TFCC損傷が関係しているかもしれません。
応急処置は“RICE法”が基本
痛みが出てすぐの対処としては、RICE(ライス)法という基本的な応急処置が役立つと言われています。
-
R(Rest=安静):無理に動かさず、負担を減らす
-
I(Ice=冷却):氷や保冷剤で冷やすことで炎症が落ち着くこともある
-
C(Compression=圧迫):包帯やサポーターで軽く圧を加える
-
E(Elevation=挙上):心臓よりも手を高く保ち、腫れの軽減を図る
これらは、理学療法士や整骨院などでも広く推奨されている基本的な方法です。
家でできる具体的なケア方法
応急処置のあと、痛みがやや落ち着いてきたら、無理のない範囲でケアを続けることが大切とされています。
-
アイシング:1日数回、10〜15分程度冷やすと良い場合がある
-
ストレッチ:手首の筋を軽く伸ばすことで血流の改善が期待されている
-
サポーター・テーピング:動きを制限して負担を軽くする工夫も
なお、無理なストレッチやマッサージは逆効果になる可能性もあるため、注意が必要です。
生活習慣の見直しも効果的
そして、意外と見落とされがちなのが生活習慣です。
パソコンを長時間使う人は、マウスの位置やキーボードとの高さを見直すだけでも手首への負担が軽減されることがあるそうです。また、スマホ操作は両手を使ったり、机の上に置いた状態で操作するなど、小さな工夫が症状の緩和に役立つ場合もあります。
さらに、定期的に手首を休める時間を意識的に取り入れることが、再発予防につながるとも言われています。
(引用元:https://www.mediaid-online.jp/clinic_notes/information/778/)
#フィンケルシュタインテスト
#TFCCチェック法
#RICE処置
#手首のセルフケア
#姿勢改善と生活習慣見直し