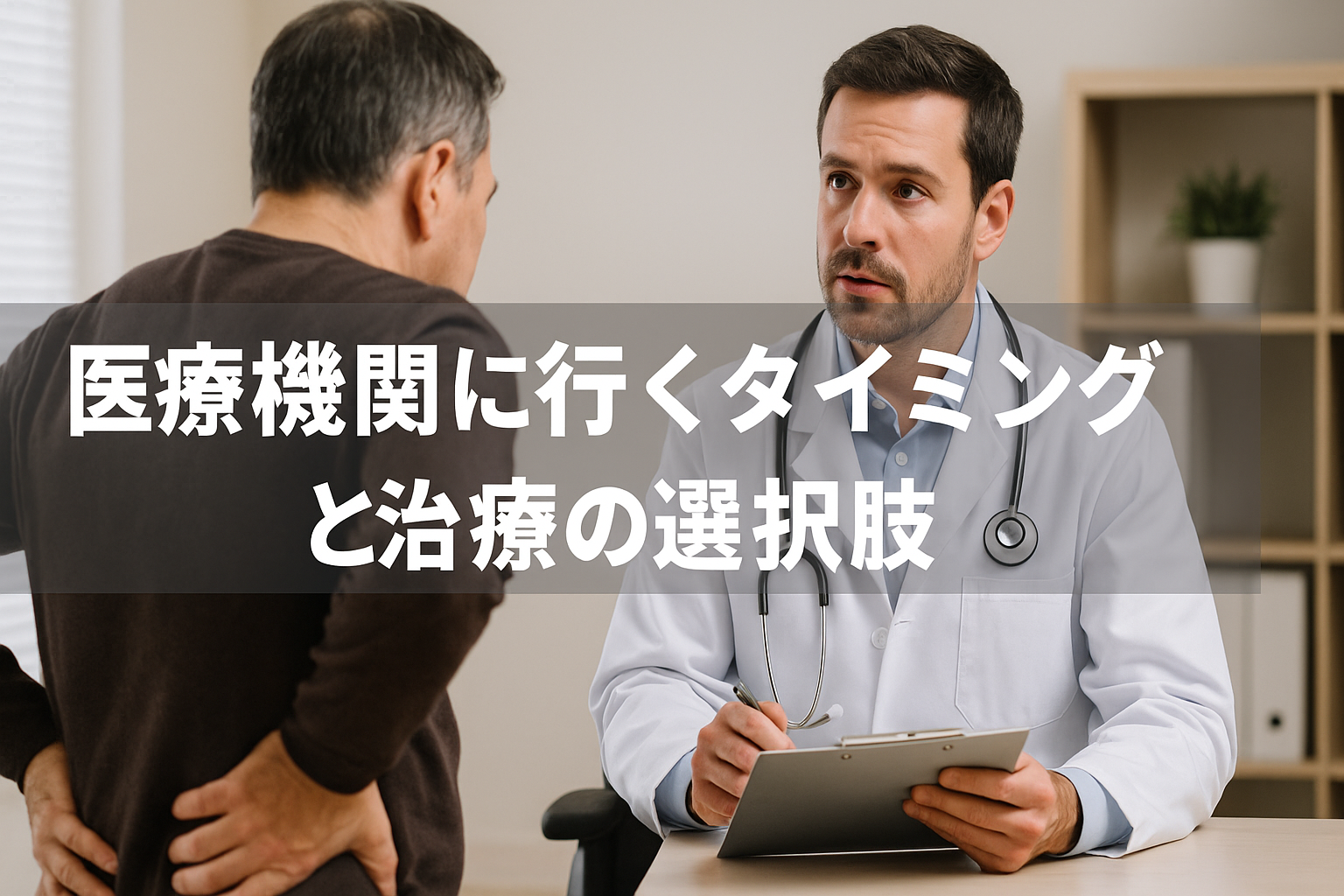坐骨神経痛とは何か?しびれの仕組みと症状の特徴
坐骨神経痛とは、お尻から太もも、ふくらはぎ、そして足先にかけて伸びる坐骨神経が圧迫や炎症などによって刺激を受けることで、痛みやしびれが現れる症状です。
「腰が痛いのとはちょっと違うな…」「足のしびれが抜けない…」といった感覚が続くとき、多くの場合この坐骨神経痛が関わっていると考えられています。
しびれのメカニズム(神経の圧迫・血流・炎症など)
坐骨神経は体の中でも特に長い神経で、腰椎から足先までを走行しています。そのため、腰やお尻の部分で椎間板や筋肉に圧迫されると、神経伝達がスムーズにいかず、しびれや感覚異常が出るとされています。さらに、炎症による血流の悪化も加わり、「じんじんする」「感覚が鈍い」といった状態を引き起こすことがあると言われています。
典型的な症状
しびれはお尻から太もも、ふくらはぎ、足の甲や足裏にかけて広がるのが一般的だといわれています。人によっては「片足だけがしびれる」「歩いていると悪化する」といった違いがあり、痛みやしびれ、さらには感覚の低下や力が入りづらいと感じることもあるようです。軽度のときは一時的に治まることもありますが、慢性化すると日常生活に大きく影響を及ぼすと言われています。
発症しやすい人(年齢、職業、生活習慣などのリスク要因)
一般的に40〜60代で発症しやすいとされ、特にデスクワークや長時間立ち仕事をする人、重い荷物を頻繁に持つ人に多い傾向です。また、運動不足や肥満もリスク因子と考えられており、腰への負担が大きい生活習慣が続くと、症状につながりやすくなります。
「最近座りっぱなしが増えた」「腰や足に違和感を覚える」など、早めに体のサインに気づくことが大切です。
(引用元:https://www.mediaid-online.jp/clinic_notes/information/1584/)
#坐骨神経痛
#しびれ
#原因と症状
#生活習慣リスク
#セルフケア
主な原因の種類
坐骨神経痛の原因にはいくつかのタイプがあると言われています。
まず代表的なのが椎間板ヘルニア。椎間板が飛び出して神経を圧迫することにより、しびれや痛みが出るケースです。次に多いのが脊柱管狭窄症。加齢や靭帯の肥厚などによって脊柱管が狭くなり、神経が圧迫される状態です。
一方、梨状筋症候群では、お尻の奥にある梨状筋という筋肉が緊張し、坐骨神経を圧迫することでしびれが出るものです。さらに腰椎すべり症の場合は、腰椎そのものがずれてしまい、神経への圧迫につながると考えられています。
しびれが出る状況・姿勢との関連性
しびれが悪化する場面も人によって違います。立っているときよりも座っているときに強く感じる人もいれば、逆に歩くとしびれが増す方もいます。また、前かがみになると悪化するタイプや、長時間立っていると症状が強まるケースもあると言われています。こうした動作としびれの関係を知ることで、原因を推測する手がかりになるので、気になる症状はメモしておくと良いでしょう。
他の疾患との鑑別
坐骨神経痛のように見えて、実際には別の病気が関わっている場合もあります。例えば、糖尿病性神経障害では両足に広がるしびれが出やすいとされていますし、末梢神経障害では局所的な感覚異常が見られることがあります。さらにまれなケースとしては骨盤内腫瘍が神経を圧迫してしびれを引き起こすこともあると考えられています。
検査
坐骨神経痛の原因を把握するためには、まず問診や視診で症状の出方を確認し、そのうえで触診が行われます。整形外科などでは必要に応じてX線やMRIなどの画像検査を用い、神経圧迫の有無や部位を確かめることもあります。
#坐骨神経痛
#原因の種類
#しびれ悪化姿勢
#他の疾患との鑑別
#触診と画像検査